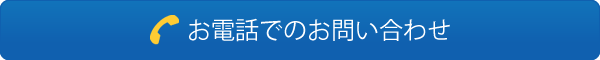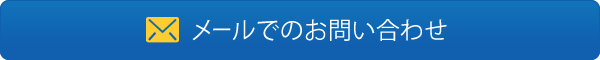【遺留分制度の見直し】
「遺留分」という言葉、聞いたことがある方、また単語は知らなくとも意味をなんとなくご存じの方は多くいらっしゃるのではないでしょうか?遺留分とは、被相続人の財産のうち、一定の範囲の相続人に認められている最低限保証された相続財産のことです。被相続人が生前、「愛人に全財産を遺贈する」と言った遺言書を作成した場合であっても、配偶者や子どもたちは財産を取得する権利を主張することができるのです。
では、その最低限保証された権利をどのように受け取ることができるのか、この点についてこの度、民法改正が入りました。
現行法:現物での返還が原則
改正後:金銭支払いの請求が可能
現行法において、遺留分権利を主張する者には金銭による弁償を選択する余地はありませんでした。以下に例を挙げてみました。
(例)
経営者であった被相続人が、事業を手伝っていた長男に会社の土地建物を相続する旨の遺言をし、死亡した。一方、長女は僅かな現金を相続した。これを不満に思った長女が遺留分を主張。

長女が遺留分を主張し、最低限認められた財産をどこから取得するのか。これは長男が相続した会社の土地建物の一部を受け取るというのがこれまでの取り扱いでした。そのため、会社の土地建物が長男と長女との共有状態になり、権利関係が非常に複雑な状態になっていしましました。
改正後、遺留分請求による生じる権利は金銭債権となるため、長男は会社の土地建物を単独所有することができ、共有関係が当然に生ずることを回避することができました。また、遺言により、目的財産を長男に遺したいという遺言者の意思も尊重することができるようになりました。
弊所では相続税専門の税理士が対応します。お困りごとがございましたらどうぞご相談ください。